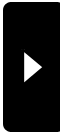2014年05月15日
喫煙禁止区域を拡大へ 岐阜市
岐阜市は13日の市環境審議会で、現在、長良橋通りなどで実施している路上喫煙禁止区域を
拡大し、来年夏にオープンする文化複合施設「みんなの森 ぎふメディアコスモス」周辺を
新たな禁止区域に指定する方針を明らかにした。
指定区域案を8月に開催される第2回環境審議会で説明して委員からの意見を聞き、
今年度中に最終案を決定。新年度から実施したいとしている。
同市自然共生政策課では「中央図書館を含むメディアコスモスは大勢の市民の利用が
予想される。ごみのポイ捨て防止など環境美化を推進するために禁止区域の指定が必要と
判断した」と説明している。
同市の路上喫煙禁止区域は、JR岐阜駅から市役所本庁舎までの長良橋通りや玉宮通り、
柳ヶ瀬本通りなどの中心部のほか、金華山登山道、岐阜公園の一部なども指定されており、
同市は2009年1月から違反者に2000円の過料を科している。
本日の担当:学園通り店 野口 (読売新聞より)
拡大し、来年夏にオープンする文化複合施設「みんなの森 ぎふメディアコスモス」周辺を
新たな禁止区域に指定する方針を明らかにした。
指定区域案を8月に開催される第2回環境審議会で説明して委員からの意見を聞き、
今年度中に最終案を決定。新年度から実施したいとしている。
同市自然共生政策課では「中央図書館を含むメディアコスモスは大勢の市民の利用が
予想される。ごみのポイ捨て防止など環境美化を推進するために禁止区域の指定が必要と
判断した」と説明している。
同市の路上喫煙禁止区域は、JR岐阜駅から市役所本庁舎までの長良橋通りや玉宮通り、
柳ヶ瀬本通りなどの中心部のほか、金華山登山道、岐阜公園の一部なども指定されており、
同市は2009年1月から違反者に2000円の過料を科している。
本日の担当:学園通り店 野口 (読売新聞より)
Posted by 保険カンパニー at
09:29
│Comments(0)
2014年05月14日
クリスマスケーキ:子どものデザインを商品化 作品募集中
菓子メーカーの銀座コージーコーナー(東京都中央区)が開催する
「2014 夢のクリスマスケーキコンテスト」のデザイン募集が今年も始まった。
「こんなクリスマスケーキがあったらいいな」というイラストを小学生から募集し、
グランプリ受賞作品を商品化するというコンテストで、今年で6年目。
昨年までは受賞作品を翌年に商品化していたが、今年からその年に募集したものを
年内に商品化するようにした。また、これまで店頭でのみ受け付けていたが、
ウェブや郵送でも受け付ける。詳しくは同コンテストのウェブサイト
(https://xmas.cozycorner.co.jp/)へ。締め切りは6月30日。
本日の担当:沼津店 山崎 (毎日新聞より)
「2014 夢のクリスマスケーキコンテスト」のデザイン募集が今年も始まった。
「こんなクリスマスケーキがあったらいいな」というイラストを小学生から募集し、
グランプリ受賞作品を商品化するというコンテストで、今年で6年目。
昨年までは受賞作品を翌年に商品化していたが、今年からその年に募集したものを
年内に商品化するようにした。また、これまで店頭でのみ受け付けていたが、
ウェブや郵送でも受け付ける。詳しくは同コンテストのウェブサイト
(https://xmas.cozycorner.co.jp/)へ。締め切りは6月30日。
本日の担当:沼津店 山崎 (毎日新聞より)
Posted by 保険カンパニー at
08:21
│Comments(0)
2014年05月13日
肥満、第3の要因に「腸内細菌の変化」 伝統的な和食で予防可能
肥満やメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)を引き起こす大きな環境要因に
食べ過ぎや運動不足が挙げられる。
3つ目の環境要因として、膨大な腸内細菌の集まりである腸内細菌叢(そう)が
関係していることが、ゲノム(全遺伝情報)解析が進んだことで明らかになってきた。
専門家は健全な腸内細菌叢を保つには欧米型の食事ではなく、伝統的な和食が
良いと推奨している。
◆米研究論文に注目
「腸内細菌叢は肥満研究の最も大きな注目分野の一つ」と語るのは、日本肥満学会
理事長で国立国際医療研究センター総長の春日雅人氏だ。糖尿病研究の権威である
春日氏は昨年9月、米科学誌『サイエンス』に掲載された米ワシントン大のグループの
研究論文に着目した。
同論文によると、片方が肥満、もう片方が痩せ形の双子4組を選び出し、腸内細菌が
大量に含まれるそれぞれの便を無菌のマウスの腸内に移植。すると、太った人の
便を移植したマウスは太り、痩せ形の人の便を移植したマウスは太らなかったという。
同論文から春日氏は「細菌叢の差違は肥満の結果もたらされたのではなく、
肥満を引き起こす原因だったことが示された」と強調する。
◆ゲノム解析で加速
ヒトゲノムの全配列は2003(平成15)年に解読が宣言された。腸内細菌叢の研究は
ゲノム解析の恩恵を受け、細菌の遺伝子配列の解析速度が飛躍的に上がり、
菌の種類や量が分かるようになった。腸内細菌叢と肥満の関係は米国が先行しているが、
日本では免疫疾患などの関係について、理化学研究所統合生命医科学研究センターの
本田賢也・消化管恒常性研究チームリーダーによる研究が知られている。
「腸内には約1千種、総重量で1キロの細菌が存在し、共生している。それらの共生関係が
崩れると、肥満・メタボといった代謝性疾患やアレルギーなどの免疫疾患につながる」と
本田氏は解説する。
共生関係を崩すものとしてはまず、脂肪が多くカロリーの高い欧米型の食事が挙げられる。
本田氏によると、高脂肪食を1週間続けただけで細菌叢の構成が変化したという
複数のデータがあり、肥満の原因となる細菌は「食事で摂取した糖類などの分解を促進し、
体内により吸収しやすい形にする働きがある。そういう菌が高脂肪食を好み、それを餌に
増えるのではないか」。
次に、食物繊維の少ない食事や、同じメニューを繰り返し食べることも共生関係を崩す。
いずれのケースも「バクテロイデスとファーミキューテスという腸内細菌のグループの細菌量が
変化して崩れる」ことが判明している。現時点で最大の予防方法は食事にあるという。
本田氏は「健全な腸内細菌叢を保つためには、野菜を含め、さまざまな食材を少しずつ
摂取できる伝統的な和食が適している」と話している。
■数十の菌を合わせた飲み薬開発に期待
腸内細菌というと、ヨーグルトの整腸作用が思い浮かぶ。
本田氏は「良い作用があるのは確かだ」と前置きしたうえで、「腸内細菌叢全体というレベルから
見ると、ヨーグルトを食べただけで大きな影響を与えられるほどでない」とみる。ビフィズス菌などは
腸内細菌の中ではマイナーな部類であることや、摂取しても体内にとどまりにくいからだ。
本田氏は現在、細菌叢の中から優れた菌の組み合わせについて研究を進めており、将来は
「数十の菌を合わせた飲み薬が開発される時代が来る」と期待をにじませた。
本日の担当:沼津店 坂倉 (産経新聞より)
食べ過ぎや運動不足が挙げられる。
3つ目の環境要因として、膨大な腸内細菌の集まりである腸内細菌叢(そう)が
関係していることが、ゲノム(全遺伝情報)解析が進んだことで明らかになってきた。
専門家は健全な腸内細菌叢を保つには欧米型の食事ではなく、伝統的な和食が
良いと推奨している。
◆米研究論文に注目
「腸内細菌叢は肥満研究の最も大きな注目分野の一つ」と語るのは、日本肥満学会
理事長で国立国際医療研究センター総長の春日雅人氏だ。糖尿病研究の権威である
春日氏は昨年9月、米科学誌『サイエンス』に掲載された米ワシントン大のグループの
研究論文に着目した。
同論文によると、片方が肥満、もう片方が痩せ形の双子4組を選び出し、腸内細菌が
大量に含まれるそれぞれの便を無菌のマウスの腸内に移植。すると、太った人の
便を移植したマウスは太り、痩せ形の人の便を移植したマウスは太らなかったという。
同論文から春日氏は「細菌叢の差違は肥満の結果もたらされたのではなく、
肥満を引き起こす原因だったことが示された」と強調する。
◆ゲノム解析で加速
ヒトゲノムの全配列は2003(平成15)年に解読が宣言された。腸内細菌叢の研究は
ゲノム解析の恩恵を受け、細菌の遺伝子配列の解析速度が飛躍的に上がり、
菌の種類や量が分かるようになった。腸内細菌叢と肥満の関係は米国が先行しているが、
日本では免疫疾患などの関係について、理化学研究所統合生命医科学研究センターの
本田賢也・消化管恒常性研究チームリーダーによる研究が知られている。
「腸内には約1千種、総重量で1キロの細菌が存在し、共生している。それらの共生関係が
崩れると、肥満・メタボといった代謝性疾患やアレルギーなどの免疫疾患につながる」と
本田氏は解説する。
共生関係を崩すものとしてはまず、脂肪が多くカロリーの高い欧米型の食事が挙げられる。
本田氏によると、高脂肪食を1週間続けただけで細菌叢の構成が変化したという
複数のデータがあり、肥満の原因となる細菌は「食事で摂取した糖類などの分解を促進し、
体内により吸収しやすい形にする働きがある。そういう菌が高脂肪食を好み、それを餌に
増えるのではないか」。
次に、食物繊維の少ない食事や、同じメニューを繰り返し食べることも共生関係を崩す。
いずれのケースも「バクテロイデスとファーミキューテスという腸内細菌のグループの細菌量が
変化して崩れる」ことが判明している。現時点で最大の予防方法は食事にあるという。
本田氏は「健全な腸内細菌叢を保つためには、野菜を含め、さまざまな食材を少しずつ
摂取できる伝統的な和食が適している」と話している。
■数十の菌を合わせた飲み薬開発に期待
腸内細菌というと、ヨーグルトの整腸作用が思い浮かぶ。
本田氏は「良い作用があるのは確かだ」と前置きしたうえで、「腸内細菌叢全体というレベルから
見ると、ヨーグルトを食べただけで大きな影響を与えられるほどでない」とみる。ビフィズス菌などは
腸内細菌の中ではマイナーな部類であることや、摂取しても体内にとどまりにくいからだ。
本田氏は現在、細菌叢の中から優れた菌の組み合わせについて研究を進めており、将来は
「数十の菌を合わせた飲み薬が開発される時代が来る」と期待をにじませた。
本日の担当:沼津店 坂倉 (産経新聞より)
Posted by 保険カンパニー at
09:40
│Comments(0)
2014年05月08日
子育てコンシェルジュ、島田市が導入1カ月 出張相談開始へ
島田市が4月に「子育てコンシェルジュ」を導入して1カ月。
保育園への入所や育児に関することなど、市内の母親や父親から少しずつ相談が
寄せられている。今後、市内10カ所の子育て支援センターへの出張もスタートし、
より積極的に子育ての悩み解消を図る。
子育てコンシェルジュは、子育てに関するあらゆる悩みの窓口となり、さまざまな
情報提供や部署間調整を通して悩みの解決を支援する専門の相談員。
子育て応援課こども相談係の稲葉美保子係長が初代子育てコンシェルジュとして
家庭児童相談室や育児サポーターなどと連携しながら、保護者の立場に寄り添った
支援を行っている。
県外から転入して一人で不安を抱えていた母親の相談に対し、市内にある
「県外出身ママの会」を紹介して喜ばれたことも。子育て世代に関わる各種事業や
制度、施設、団体、イベントなどを知り尽くしているからこそできるサポートは多い。
稲葉さんは「庁内に相談の集約場所ができたので縦割りの解消にも手応えがある。
子育てのことは何でもまずコンシェルジュに聞けばいいという意識が市民の間に
広まってくれたら」と願っている。
本日の担当:学園通り店 杉山 (静岡新聞より)
保育園への入所や育児に関することなど、市内の母親や父親から少しずつ相談が
寄せられている。今後、市内10カ所の子育て支援センターへの出張もスタートし、
より積極的に子育ての悩み解消を図る。
子育てコンシェルジュは、子育てに関するあらゆる悩みの窓口となり、さまざまな
情報提供や部署間調整を通して悩みの解決を支援する専門の相談員。
子育て応援課こども相談係の稲葉美保子係長が初代子育てコンシェルジュとして
家庭児童相談室や育児サポーターなどと連携しながら、保護者の立場に寄り添った
支援を行っている。
県外から転入して一人で不安を抱えていた母親の相談に対し、市内にある
「県外出身ママの会」を紹介して喜ばれたことも。子育て世代に関わる各種事業や
制度、施設、団体、イベントなどを知り尽くしているからこそできるサポートは多い。
稲葉さんは「庁内に相談の集約場所ができたので縦割りの解消にも手応えがある。
子育てのことは何でもまずコンシェルジュに聞けばいいという意識が市民の間に
広まってくれたら」と願っている。
本日の担当:学園通り店 杉山 (静岡新聞より)
Posted by 保険カンパニー at
09:19
│Comments(0)
2014年05月07日
子供の人口、前年比16万人減…33年連続減少
5日の「こどもの日」にあわせ、総務省が4日に発表した15歳未満の
子供の推計人口(4月1日現在)は、前年比16万人減の1633万人となった。
子供の減少は33年連続で、比較可能な1950年以降、最少を更新した。
総人口(1億2714万人)に占める子供の割合も前年比0・1ポイント減の12・8%と
40年連続で減少し、過去最低となった。
内訳は、男子が836万人、女子が797万人だった。3歳ごとの年齢区分では、
12~14歳が351万人、9~11歳が333万人、6~8歳が319万人、3~5歳が316万人、
0~2歳が314万人で、年齢が下がるごとに減っている。
昨年10月1日現在の都道府県別の子供の割合は、最高が沖縄県の17・6%、
最低は秋田県の10・9%。前年より子供の数が増えたのは沖縄県と東京都だけだった。
残りの45道府県はいずれも前年より減少したが、このうち減少幅が縮小したのは11県で、
東日本大震災の影響で落ち込みが激しかった福島県が最も改善した。
本日の担当:学園通り店 長山 (読売新聞より)
子供の推計人口(4月1日現在)は、前年比16万人減の1633万人となった。
子供の減少は33年連続で、比較可能な1950年以降、最少を更新した。
総人口(1億2714万人)に占める子供の割合も前年比0・1ポイント減の12・8%と
40年連続で減少し、過去最低となった。
内訳は、男子が836万人、女子が797万人だった。3歳ごとの年齢区分では、
12~14歳が351万人、9~11歳が333万人、6~8歳が319万人、3~5歳が316万人、
0~2歳が314万人で、年齢が下がるごとに減っている。
昨年10月1日現在の都道府県別の子供の割合は、最高が沖縄県の17・6%、
最低は秋田県の10・9%。前年より子供の数が増えたのは沖縄県と東京都だけだった。
残りの45道府県はいずれも前年より減少したが、このうち減少幅が縮小したのは11県で、
東日本大震災の影響で落ち込みが激しかった福島県が最も改善した。
本日の担当:学園通り店 長山 (読売新聞より)
Posted by 保険カンパニー at
10:04
│Comments(0)