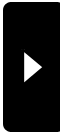2015年05月29日
パチンコで認知症予防
◆桐生の会社開発 手を動かし脳に刺激
光や音で娯楽を演出するパチンコを介護現場で役立てようと、桐生市の中古パチンコ台販売会社が、
福祉向けの台の開発を続けている。先月末からは市内のデイケア施設など2か所に試験的に設置。
関係者は、玉の方向を考えたり、指先の力を調節したりすることが認知症予防につながると期待する。
「あらやだ。大当たりがきちゃったわよ」。桐生市川内町の通所介護施設「モン・クール」に週2回
通っている片所かたしょ豊子さん(90)が声を弾ませた。
広場の脇に設置された台が赤く点滅し、玉を引き込む中央の「羽」がパタパタと動き出す。
「ここからの微妙な力加減が難しいのよ。どこに打てば入るかって考えながら打つから夢中になっちゃう」と、
玉の行方を真剣に見つめる。
施設長を務める柿沼博昭さん(47)は「試験的に導入したが、予想以上に楽しんでいる人が多い。
考えながら指先を動かすのでリハビリにもなります」と振り返った。
台を設置したのは、全国に中古台を通信販売する「グローバルスタンダード」(桐生市小梅町)。
利用者が玉を口に入れないように受け皿の上にアクリルのカバーを付け、音や光も控えめに調整した。
社長の野口智行さん(32)が介護現場向けの台の開発を始めたのは、2年前。テレビ番組で
「お年寄りがゲームセンターに集まっている」というニュースを見たことがきっかけだった。
同時期に、全国の老人福祉施設からの注文も増え、本格的な開発を始めた。
軟らかいボールを握る動きや、カスタネットを鳴らす動きなど、介護現場でリハビリとして導入されている
動作を使った操作方法も開発しており、今後、実用化を検討する。
野口さんは、「パチンコというとギャンブルというイメージを持つ人もいるが、目や耳、手足を複合的に
動かすことで脳の刺激にもなる。パチンコを経験した施設利用者も増えるので、専門家にも意見を
聞きながら開発を続けたい」と話した。
高崎健康福祉大保健医療学部講師で、理学療法士の山上徹也さん(36)は「玉の行方を考えることは、
注意力や集中力をつかさどる前頭葉の刺激になり、認知症の予防につながるのではないか。
点数を表示すると競争意識も芽生え、効果が高まると考えられる」と分析した。
本日の担当:御殿場店 池谷 (読売新聞より)
光や音で娯楽を演出するパチンコを介護現場で役立てようと、桐生市の中古パチンコ台販売会社が、
福祉向けの台の開発を続けている。先月末からは市内のデイケア施設など2か所に試験的に設置。
関係者は、玉の方向を考えたり、指先の力を調節したりすることが認知症予防につながると期待する。
「あらやだ。大当たりがきちゃったわよ」。桐生市川内町の通所介護施設「モン・クール」に週2回
通っている片所かたしょ豊子さん(90)が声を弾ませた。
広場の脇に設置された台が赤く点滅し、玉を引き込む中央の「羽」がパタパタと動き出す。
「ここからの微妙な力加減が難しいのよ。どこに打てば入るかって考えながら打つから夢中になっちゃう」と、
玉の行方を真剣に見つめる。
施設長を務める柿沼博昭さん(47)は「試験的に導入したが、予想以上に楽しんでいる人が多い。
考えながら指先を動かすのでリハビリにもなります」と振り返った。
台を設置したのは、全国に中古台を通信販売する「グローバルスタンダード」(桐生市小梅町)。
利用者が玉を口に入れないように受け皿の上にアクリルのカバーを付け、音や光も控えめに調整した。
社長の野口智行さん(32)が介護現場向けの台の開発を始めたのは、2年前。テレビ番組で
「お年寄りがゲームセンターに集まっている」というニュースを見たことがきっかけだった。
同時期に、全国の老人福祉施設からの注文も増え、本格的な開発を始めた。
軟らかいボールを握る動きや、カスタネットを鳴らす動きなど、介護現場でリハビリとして導入されている
動作を使った操作方法も開発しており、今後、実用化を検討する。
野口さんは、「パチンコというとギャンブルというイメージを持つ人もいるが、目や耳、手足を複合的に
動かすことで脳の刺激にもなる。パチンコを経験した施設利用者も増えるので、専門家にも意見を
聞きながら開発を続けたい」と話した。
高崎健康福祉大保健医療学部講師で、理学療法士の山上徹也さん(36)は「玉の行方を考えることは、
注意力や集中力をつかさどる前頭葉の刺激になり、認知症の予防につながるのではないか。
点数を表示すると競争意識も芽生え、効果が高まると考えられる」と分析した。
本日の担当:御殿場店 池谷 (読売新聞より)
Posted by 保険カンパニー at
09:13
│Comments(0)
2015年05月28日
医療保険制度改革関連法が成立
赤字が続く国民健康保険の財政基盤を強化するため、平成30年度に運営主体を市町村から
都道府県に移すことを柱とした医療保険制度改革関連法が、27日の参議院本会議で
自民・公明両党などの賛成多数で可決され、成立しました。
医療保険制度改革関連法は、高齢者の比率が高く、年間3000億円を超える赤字が続いている
国民健康保険の財政基盤を強化するため、国が行う財政支援を拡充したうえで、平成30年度に
運営主体を市町村から都道府県に移すことを柱としています。
そして、国の財政支援の財源を確保するため、今年度から3年かけて、大企業のサラリーマンらが
加入する健康保険組合の負担を段階的に引き上げるとしています。
また、負担の公平を図るため、一般病床に入院している患者の食事代について、自己負担額を
段階的に引き上げるほか、紹介状なしで大病院を受診する患者の自己負担について、
「5000円から1万円」の金額を目安に負担を求めるとしています。
さらに、健康保険が適用される診療と適用されない診療を合わせて行う「混合診療」の範囲を拡大し、
患者からの申し出を受けて、新しい治療や投薬を実施できるようにする制度を創設するとしています。
医療保険制度改革関連法は27日の参議院本会議で採決が行われ、自民・公明両党などの
賛成多数で可決され、成立しました。
本日の担当:沼津店 鈴木勝(NHKニュースより)
都道府県に移すことを柱とした医療保険制度改革関連法が、27日の参議院本会議で
自民・公明両党などの賛成多数で可決され、成立しました。
医療保険制度改革関連法は、高齢者の比率が高く、年間3000億円を超える赤字が続いている
国民健康保険の財政基盤を強化するため、国が行う財政支援を拡充したうえで、平成30年度に
運営主体を市町村から都道府県に移すことを柱としています。
そして、国の財政支援の財源を確保するため、今年度から3年かけて、大企業のサラリーマンらが
加入する健康保険組合の負担を段階的に引き上げるとしています。
また、負担の公平を図るため、一般病床に入院している患者の食事代について、自己負担額を
段階的に引き上げるほか、紹介状なしで大病院を受診する患者の自己負担について、
「5000円から1万円」の金額を目安に負担を求めるとしています。
さらに、健康保険が適用される診療と適用されない診療を合わせて行う「混合診療」の範囲を拡大し、
患者からの申し出を受けて、新しい治療や投薬を実施できるようにする制度を創設するとしています。
医療保険制度改革関連法は27日の参議院本会議で採決が行われ、自民・公明両党などの
賛成多数で可決され、成立しました。
本日の担当:沼津店 鈴木勝(NHKニュースより)
Posted by 保険カンパニー at
09:29
│Comments(0)
2015年05月27日
若者の「田園回帰」で農村活性化を…農業白書
政府は26日、2014年度の農業白書(食料・農業・農村の動向)を閣議決定した。
今回、人口減社会を特集として初めて取り上げた。2010年に約4200万人だった農村人口は、
40年には約3200万人まで2割超減ると推計。農村を支えている高齢者(65歳以上)も
25年からは減少に転じるとの見通しを示し、都市に住む若者を農村に呼び寄せる「田園回帰」の
動きなどを後押しして、農村を活性化すべきだと指摘した。
白書は、このままでは「農地などの資源やコミュニティーの維持が困難になる」と懸念を示した。
一方で、14年の内閣府の調査によると、都市住民の約32%が農山漁村地域への定住願望に
ついて「ある」と答え、約21%だった05年の前回調査より大幅に増えた。
特に20歳代男性では47%強に上っているという。
白書は「若者を中心に『田園回帰』の動きや、定年退職を契機とした農村への定住志向が
みられる」と指摘し、「農業・農村の潜在力を最大限に発揮し、産業の育成や雇用の確保、所得の
増大を図ることが重要」だとした。実例として、地元の農産品の販売に力を入れる高知県四万十町の
事例などを紹介した。
林農相は26日の閣議後の記者会見で、「定住に結びつけることが大事で、地域の主体的な
取り組みを後押しする政策を推進したい」と述べた。
本日の担当:沼津店 山崎 (読売新聞より)
今回、人口減社会を特集として初めて取り上げた。2010年に約4200万人だった農村人口は、
40年には約3200万人まで2割超減ると推計。農村を支えている高齢者(65歳以上)も
25年からは減少に転じるとの見通しを示し、都市に住む若者を農村に呼び寄せる「田園回帰」の
動きなどを後押しして、農村を活性化すべきだと指摘した。
白書は、このままでは「農地などの資源やコミュニティーの維持が困難になる」と懸念を示した。
一方で、14年の内閣府の調査によると、都市住民の約32%が農山漁村地域への定住願望に
ついて「ある」と答え、約21%だった05年の前回調査より大幅に増えた。
特に20歳代男性では47%強に上っているという。
白書は「若者を中心に『田園回帰』の動きや、定年退職を契機とした農村への定住志向が
みられる」と指摘し、「農業・農村の潜在力を最大限に発揮し、産業の育成や雇用の確保、所得の
増大を図ることが重要」だとした。実例として、地元の農産品の販売に力を入れる高知県四万十町の
事例などを紹介した。
林農相は26日の閣議後の記者会見で、「定住に結びつけることが大事で、地域の主体的な
取り組みを後押しする政策を推進したい」と述べた。
本日の担当:沼津店 山崎 (読売新聞より)
Posted by 保険カンパニー at
08:29
│Comments(0)
2015年05月25日
日本初のチョコレート摂取による大規模研究
チョコレートやココアに含まれるカカオポリフェノールには活性酸素を抑える働きがあり、
高血圧や高コレステロールなどの生活習慣病に有効だという話はどこかでお聞きになったことが
あるかもしれない。だが、それに加え、うつ病やアルツハイマー型認知症の改善、記憶・学習などの
認知機能向上にもカカオポリフェノールが役立つ可能性が高いとしたら?
極めて興味深いその内容は、愛知県蒲郡市、愛知学院大学、明治大学が、産官学共同で
平成26年3月から行ってきた「チョコレート摂取による健康効果に関する実証研究」の最終報告の
まとめとして、5月19日に東京国際フォーラムで発表された。
この実証研究は、「蒲郡市ヘルスケア計画」に基づく取り組みとして行われ、蒲郡市内外の
45~69歳までの347人(男性123人、女性224人)に、カカオポリフェノールを多く含むチョコレートを、
4週間毎日、一定量(25g)摂取してもらい、摂取前後の血圧や血液成分など体の状態の変化を
検証するというもの。
平成26年11月の中間報告では、チョコレートが血圧高めの人の血圧を低下させることや、
HDL(善玉)コレステロールを上昇させることが報告された。精神的にも肉体的にも活動的になると
いう効果も確認されているが、体重やBMI値には変化がないことなども発表されて話題を呼んだ。
そして最終報告では、さらに注目すべき事項が確認された。
研究を監修した愛知学院大学心身科学部の大澤俊彦教授によると、カギとなったのは被験者の
BDNF(Brain-derived neurotrophic factor:脳由来神経栄養因子)が、チョコレートの摂取前後で
有意に上昇したという検査結果。BDNFはタンパク質の一種で、脳内で記憶を司る海馬に多く
含まれる物質だが、加齢とともに減少する。うつ病や認知症の診断では負の相関(病状が重い患者ほど
BDNF濃度が低い)が見られたり、マウス実験ではBDNFが少ないと記憶や学習能力が低下したり
することから、認知機能に重要な関連性があると考えられている。記憶や学習などの認知機能を促進させる
物質がチョコレートを食べると増えるということは、認知症を予防する可能性があるということ。
さらに、カカオポリフェノールには脳血流量を上昇させる効果があることがわかっているが、脳血流量の
上昇でもBDNFが増加するという報告もある。抗酸化佐藤と血流量増加の両面からBDNFが増加し、
認知機能が上昇することで、認知症予防が期待されるというわけだ。
最終報告で発表されたもうひとつの大きなトピックは、チョコレートの摂取前後で、動脈硬化などの
検査などで使われる炎症指標(Hs-CRP)と酸化ストレス指標(8-OHdG)が、第3四分位以上の人で
低下したということ。つまり被験者のうち、動脈硬化を引き起こす要因となる血管内皮機能低下リスクが
高いと思われる順に(2つの指標の値が大きい順に)上から四分の一までの人が、チョコレートを
摂取することで数字を改善したという。すなわち、ポリフェノールの抗酸化作用が裏付けられ、
チョコレートには動脈硬化のリスクを低減させる効果があることが示唆されたわけだ。ちなみに数値の
悪くない人も含めた被験者全員では、有意差は確認されていない。
アジア系人種としては初となるこの大規模なチョコレート摂取調査が明らかにした結果は、重要なものが
多い。血圧に関しては、正常血圧の人は変化が小さく、高血圧の人ほどチョコレートで血圧が下がるという
理想的な結果が出たし、蒲郡市での調査は欧米の実験と違って高カカオポリフェノールのチョコレートを
少量摂取する方法をとったので、肥満などの悪影響が出なかったという。さらに、カカオポリフェノールは
善玉コレステロールを増やすだけでなく、抗酸化作用で動脈硬化の発症を遅延させると考えられることや、
「脳の栄養」ともいわれるBDNF量を上昇させ、高ストレス社会や高齢化社会に対抗する可能性を
見出したことなどの意義は大きい。日本人のチョコレート消費量は年間約2kgで、欧米に比べると五分の
一程度だという。さまざまな効用が明らかになったいま、われわれはカカオポリフェノールをもっと
活用してもいいのかもしれない。
本日の担当:沼津店 坂倉 (ライブドアニュースより)
高血圧や高コレステロールなどの生活習慣病に有効だという話はどこかでお聞きになったことが
あるかもしれない。だが、それに加え、うつ病やアルツハイマー型認知症の改善、記憶・学習などの
認知機能向上にもカカオポリフェノールが役立つ可能性が高いとしたら?
極めて興味深いその内容は、愛知県蒲郡市、愛知学院大学、明治大学が、産官学共同で
平成26年3月から行ってきた「チョコレート摂取による健康効果に関する実証研究」の最終報告の
まとめとして、5月19日に東京国際フォーラムで発表された。
この実証研究は、「蒲郡市ヘルスケア計画」に基づく取り組みとして行われ、蒲郡市内外の
45~69歳までの347人(男性123人、女性224人)に、カカオポリフェノールを多く含むチョコレートを、
4週間毎日、一定量(25g)摂取してもらい、摂取前後の血圧や血液成分など体の状態の変化を
検証するというもの。
平成26年11月の中間報告では、チョコレートが血圧高めの人の血圧を低下させることや、
HDL(善玉)コレステロールを上昇させることが報告された。精神的にも肉体的にも活動的になると
いう効果も確認されているが、体重やBMI値には変化がないことなども発表されて話題を呼んだ。
そして最終報告では、さらに注目すべき事項が確認された。
研究を監修した愛知学院大学心身科学部の大澤俊彦教授によると、カギとなったのは被験者の
BDNF(Brain-derived neurotrophic factor:脳由来神経栄養因子)が、チョコレートの摂取前後で
有意に上昇したという検査結果。BDNFはタンパク質の一種で、脳内で記憶を司る海馬に多く
含まれる物質だが、加齢とともに減少する。うつ病や認知症の診断では負の相関(病状が重い患者ほど
BDNF濃度が低い)が見られたり、マウス実験ではBDNFが少ないと記憶や学習能力が低下したり
することから、認知機能に重要な関連性があると考えられている。記憶や学習などの認知機能を促進させる
物質がチョコレートを食べると増えるということは、認知症を予防する可能性があるということ。
さらに、カカオポリフェノールには脳血流量を上昇させる効果があることがわかっているが、脳血流量の
上昇でもBDNFが増加するという報告もある。抗酸化佐藤と血流量増加の両面からBDNFが増加し、
認知機能が上昇することで、認知症予防が期待されるというわけだ。
最終報告で発表されたもうひとつの大きなトピックは、チョコレートの摂取前後で、動脈硬化などの
検査などで使われる炎症指標(Hs-CRP)と酸化ストレス指標(8-OHdG)が、第3四分位以上の人で
低下したということ。つまり被験者のうち、動脈硬化を引き起こす要因となる血管内皮機能低下リスクが
高いと思われる順に(2つの指標の値が大きい順に)上から四分の一までの人が、チョコレートを
摂取することで数字を改善したという。すなわち、ポリフェノールの抗酸化作用が裏付けられ、
チョコレートには動脈硬化のリスクを低減させる効果があることが示唆されたわけだ。ちなみに数値の
悪くない人も含めた被験者全員では、有意差は確認されていない。
アジア系人種としては初となるこの大規模なチョコレート摂取調査が明らかにした結果は、重要なものが
多い。血圧に関しては、正常血圧の人は変化が小さく、高血圧の人ほどチョコレートで血圧が下がるという
理想的な結果が出たし、蒲郡市での調査は欧米の実験と違って高カカオポリフェノールのチョコレートを
少量摂取する方法をとったので、肥満などの悪影響が出なかったという。さらに、カカオポリフェノールは
善玉コレステロールを増やすだけでなく、抗酸化作用で動脈硬化の発症を遅延させると考えられることや、
「脳の栄養」ともいわれるBDNF量を上昇させ、高ストレス社会や高齢化社会に対抗する可能性を
見出したことなどの意義は大きい。日本人のチョコレート消費量は年間約2kgで、欧米に比べると五分の
一程度だという。さまざまな効用が明らかになったいま、われわれはカカオポリフェノールをもっと
活用してもいいのかもしれない。
本日の担当:沼津店 坂倉 (ライブドアニュースより)
Posted by 保険カンパニー at
09:15
│Comments(0)
2015年05月22日
なぜ大腸がんが急増しているのか?
俳優の今井雅之さん(54)が末期の大腸がんであることを告白し、5月に予定されていた舞台を降板した。
女優の坂口良子さん(享年57)、俳優の原田芳雄さん(享年71)はこの病気で亡くなっている。
一方で、ジャーナリストの鳥越俊太郎さん(75)のように、直腸がんが肺、肝臓に転移しながらも、
すべて手術で取り除くことでがんを克服した人もおり、今井さんも仕事への復帰へ強い意欲を見せている。
今井さんのように大腸がんになる患者は増えており、国立がん研究センターが公表した2015年の
がん統計予測では、これまでトップだった胃がんを抜いて、男女合わせて患者数が最も多いがんになるようだ。
今年大腸がんと診断される人は13万5800人程度いると予測されている。大腸がんは女性より男性に多い
ものの、2013年に女性のがんで最も死亡数が多かったのも大腸がんだった。女性は乳がんや子宮がんが
多いというイメージがあるかもしれないが、実は、最も女性の命を奪っているがんは大腸がんなのだ。
ちなみに、男性の場合、今のところ肺がんと胃がんのほうが死亡数は多く、第3位が大腸がんだ。
なぜ、大腸がんが増えているのか。増えている原因として専門家の多くが指摘するのが食生活や
ライフスタイルの欧米化だ。大腸がんは、がんが発生した部位によって結腸がんと直腸がんに分けられるが、
かつて日本人の結腸がんは欧米に比べて少なかった。ハワイに移民した日系人の結腸がん罹患率を
調べると、ハワイ在住の白人と同程度であり、結腸がんの発生には食生活などが大きく関わっているという
根拠になっていたのだ。ところが、日本人の食生活やライフスタイルが欧米化したことによって、すでに
日本人の結腸がん罹患率は、ハワイの日系人、アメリカの白人やイギリス人と同程度になってしまった。
国内外の研究で、大腸がんの確実な危険因子とされているのは、次の6つの項目だ。
□ 肥満
□ 喫煙習慣
□ 大量飲酒の習慣
□ 牛・豚・羊などの赤肉、ベーコン・ハム・ソーセージなど加工品の過剰摂取
□ 運動不足
□ 祖父母、親や兄弟姉妹など直系の家族に大腸がんの人がいる
大腸がんの増加は、肥満、大量飲酒の習慣、赤肉や加工品の過剰摂取、運動不足の人が増えたことと
関係がありそうだ。特に、国際的に、大腸がんのリスクを確実に下げると評価されているのが「運動」である。
世界がん研究基金と米国がん研究財団がまとめた『食物・栄養・身体活動とがん予防』(2011年版)では、
ニンニク、牛乳、カルシウムの摂取も予防効果がある「可能性大」とされているが、運動は、食物繊維が
豊富な食物とともに、「確実な予防法」にリストアップされている。
大腸のがんの発生と運動が関係あるとは意外な気がするものの、日本人を対象にした国立がん
研究センターの研究班による多目的コホート研究でも、特に男性で身体活動量の多い人は結腸がんに
なるリスクが少ないことが証明されている。日常的にほとんど運動しない身体活動量最少グループが
結腸がんになるリスクを1とすると、日常的によく運動あるいは肉体労働をしているグループの男性はリスクが
0.58倍、女性では0.82倍だった。男性の場合、運動によって結腸がん発生リスクを42%も低下させると
いうことだ。最近、デスクワークなどで長時間座り過ぎのセデンタリー症候群が、生活習慣病を増やすと問題に
なっているが、座り過ぎは結腸がんのリスクも増やす。必要だと分かっていても3日坊主で終わりがちなのが
運動だが、週1回程度定期的なスポーツを行うだけでも結腸がんのリスクは下げられるという。通勤時や
会社の中では、エスカレーターやエレベーターをなるべく使わず階段を利用するなど日常生活の中でこまめに
体を動かすことも重要だ。
ただ、日常的に運動し、禁煙、禁酒、減量、食物繊維の多い食事を心がけたとしても、大腸がんになる
リスクはゼロにはならない。早期に発見されればほぼ100%近く治るがんなので、40歳以上の人は年1回、
大腸がん検診を受けることも大切とされる。大腸がん検診は、便の中に血が混じっていないか調べる
便潜血検査で、40歳以上の人が年1回受けることで死亡率を下げることが科学的に証明されている。
ほとんどの自治体で便潜血検査を実施しているので、受けたことのない人は自治体に問い合わせてみると
よいだろう。
大腸がん検診には、肛門から内視鏡を入れる大腸内視鏡検査を受ける方法もある。
内視鏡検査による検診も死亡率を下げることが分かっているが、内視鏡検査を実施する医師の力量にも
差があり、どこでもできるわけではないので、こちらは希望者が任意で受ける検診に位置付けられている。
特に、血縁者に大腸がんになった人がいる場合には、40歳以上になったら1度、大腸内視鏡検査を
受けてみるとよいだろう。
便潜血検査で「陽性」が出たら、できるだけ早く精密検査を受けることも大切だ。「本当にがんだったら
怖いから」と放置してしまう人は意外と多く、やっと重い腰を上げて精密検査を受けたときには大腸がんが
進行していたというケースもある。便潜血検査が陽性だからといって、絶対にがんとは限らないので、
あまり怖がり過ぎないようにしよう。内視鏡検査で大腸ポリープや超早期がんが見つかったときには、
そのまま内視鏡でがんを切除できる場合もある。
精密検査を受ける際、注意したいのは、内視鏡検査は大腸がんの内視鏡治療の実績のある医療機関で
受けることだ。大腸内視鏡による治療で済めば、開腹手術を受けるよりかなり楽とはいえ、内視鏡検査の
前には2リットルの下剤を飲んで大腸を空になければならない。さらに肛門から何度も内視鏡を挿入されるのは
気持ちがよいものではない。検査と治療が一度に済むならそれに越したことはないわけだ。
内視鏡治療では取り切れないくらいがんが広がっていれば、外科手術の対象となる。リンパ節に転移が
ある場合は、一般的に、手術の後に抗がん剤治療によって再発を予防する。大腸にがんが再発したり、
肺や肝臓といった他の臓器への転移が見つかったりしても、手術で取り切れれば完治が望める場合もある。
大腸癌研究会のデータによると、他の臓器に転移があったり腹膜にがんが広がっていたりする人の
5年生存率は13%と確かに厳しいが、新しい薬が次々開発され、大腸がんの治療成績は確実に上がりつつある。
本日の担当:御殿場店 鈴木 (PRESIDENT Onlineより)
女優の坂口良子さん(享年57)、俳優の原田芳雄さん(享年71)はこの病気で亡くなっている。
一方で、ジャーナリストの鳥越俊太郎さん(75)のように、直腸がんが肺、肝臓に転移しながらも、
すべて手術で取り除くことでがんを克服した人もおり、今井さんも仕事への復帰へ強い意欲を見せている。
今井さんのように大腸がんになる患者は増えており、国立がん研究センターが公表した2015年の
がん統計予測では、これまでトップだった胃がんを抜いて、男女合わせて患者数が最も多いがんになるようだ。
今年大腸がんと診断される人は13万5800人程度いると予測されている。大腸がんは女性より男性に多い
ものの、2013年に女性のがんで最も死亡数が多かったのも大腸がんだった。女性は乳がんや子宮がんが
多いというイメージがあるかもしれないが、実は、最も女性の命を奪っているがんは大腸がんなのだ。
ちなみに、男性の場合、今のところ肺がんと胃がんのほうが死亡数は多く、第3位が大腸がんだ。
なぜ、大腸がんが増えているのか。増えている原因として専門家の多くが指摘するのが食生活や
ライフスタイルの欧米化だ。大腸がんは、がんが発生した部位によって結腸がんと直腸がんに分けられるが、
かつて日本人の結腸がんは欧米に比べて少なかった。ハワイに移民した日系人の結腸がん罹患率を
調べると、ハワイ在住の白人と同程度であり、結腸がんの発生には食生活などが大きく関わっているという
根拠になっていたのだ。ところが、日本人の食生活やライフスタイルが欧米化したことによって、すでに
日本人の結腸がん罹患率は、ハワイの日系人、アメリカの白人やイギリス人と同程度になってしまった。
国内外の研究で、大腸がんの確実な危険因子とされているのは、次の6つの項目だ。
□ 肥満
□ 喫煙習慣
□ 大量飲酒の習慣
□ 牛・豚・羊などの赤肉、ベーコン・ハム・ソーセージなど加工品の過剰摂取
□ 運動不足
□ 祖父母、親や兄弟姉妹など直系の家族に大腸がんの人がいる
大腸がんの増加は、肥満、大量飲酒の習慣、赤肉や加工品の過剰摂取、運動不足の人が増えたことと
関係がありそうだ。特に、国際的に、大腸がんのリスクを確実に下げると評価されているのが「運動」である。
世界がん研究基金と米国がん研究財団がまとめた『食物・栄養・身体活動とがん予防』(2011年版)では、
ニンニク、牛乳、カルシウムの摂取も予防効果がある「可能性大」とされているが、運動は、食物繊維が
豊富な食物とともに、「確実な予防法」にリストアップされている。
大腸のがんの発生と運動が関係あるとは意外な気がするものの、日本人を対象にした国立がん
研究センターの研究班による多目的コホート研究でも、特に男性で身体活動量の多い人は結腸がんに
なるリスクが少ないことが証明されている。日常的にほとんど運動しない身体活動量最少グループが
結腸がんになるリスクを1とすると、日常的によく運動あるいは肉体労働をしているグループの男性はリスクが
0.58倍、女性では0.82倍だった。男性の場合、運動によって結腸がん発生リスクを42%も低下させると
いうことだ。最近、デスクワークなどで長時間座り過ぎのセデンタリー症候群が、生活習慣病を増やすと問題に
なっているが、座り過ぎは結腸がんのリスクも増やす。必要だと分かっていても3日坊主で終わりがちなのが
運動だが、週1回程度定期的なスポーツを行うだけでも結腸がんのリスクは下げられるという。通勤時や
会社の中では、エスカレーターやエレベーターをなるべく使わず階段を利用するなど日常生活の中でこまめに
体を動かすことも重要だ。
ただ、日常的に運動し、禁煙、禁酒、減量、食物繊維の多い食事を心がけたとしても、大腸がんになる
リスクはゼロにはならない。早期に発見されればほぼ100%近く治るがんなので、40歳以上の人は年1回、
大腸がん検診を受けることも大切とされる。大腸がん検診は、便の中に血が混じっていないか調べる
便潜血検査で、40歳以上の人が年1回受けることで死亡率を下げることが科学的に証明されている。
ほとんどの自治体で便潜血検査を実施しているので、受けたことのない人は自治体に問い合わせてみると
よいだろう。
大腸がん検診には、肛門から内視鏡を入れる大腸内視鏡検査を受ける方法もある。
内視鏡検査による検診も死亡率を下げることが分かっているが、内視鏡検査を実施する医師の力量にも
差があり、どこでもできるわけではないので、こちらは希望者が任意で受ける検診に位置付けられている。
特に、血縁者に大腸がんになった人がいる場合には、40歳以上になったら1度、大腸内視鏡検査を
受けてみるとよいだろう。
便潜血検査で「陽性」が出たら、できるだけ早く精密検査を受けることも大切だ。「本当にがんだったら
怖いから」と放置してしまう人は意外と多く、やっと重い腰を上げて精密検査を受けたときには大腸がんが
進行していたというケースもある。便潜血検査が陽性だからといって、絶対にがんとは限らないので、
あまり怖がり過ぎないようにしよう。内視鏡検査で大腸ポリープや超早期がんが見つかったときには、
そのまま内視鏡でがんを切除できる場合もある。
精密検査を受ける際、注意したいのは、内視鏡検査は大腸がんの内視鏡治療の実績のある医療機関で
受けることだ。大腸内視鏡による治療で済めば、開腹手術を受けるよりかなり楽とはいえ、内視鏡検査の
前には2リットルの下剤を飲んで大腸を空になければならない。さらに肛門から何度も内視鏡を挿入されるのは
気持ちがよいものではない。検査と治療が一度に済むならそれに越したことはないわけだ。
内視鏡治療では取り切れないくらいがんが広がっていれば、外科手術の対象となる。リンパ節に転移が
ある場合は、一般的に、手術の後に抗がん剤治療によって再発を予防する。大腸にがんが再発したり、
肺や肝臓といった他の臓器への転移が見つかったりしても、手術で取り切れれば完治が望める場合もある。
大腸癌研究会のデータによると、他の臓器に転移があったり腹膜にがんが広がっていたりする人の
5年生存率は13%と確かに厳しいが、新しい薬が次々開発され、大腸がんの治療成績は確実に上がりつつある。
本日の担当:御殿場店 鈴木 (PRESIDENT Onlineより)
Posted by 保険カンパニー at
09:23
│Comments(0)