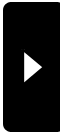2014年08月29日
運動選手のトレーニング 予防医療に応用
運動選手向けという受け止め方が強かったファンクショナルトレーニング(ファントレ)を、
一般向けのからだづくりに役立てようという動きが広がっている。
フィットネスクラブで取り入れる例が増えているだけでなく、医療機関も注目し始めた。
同トレーニングは「動きの質をあげる」とよくいわれるが、どんな特徴があり、どういった点に
気をつければよいのだろうか。
ファンクショナルトレーニングは直訳すると機能的なトレーニングだが、関節や筋肉を
効果的に使って目的に合わせた動きができるからだづくりをめざす。
筋トレとは違い「人間が生きる上で必要な、動きのトレーニングだ。正しい身体の知識を理解し、
何のために鍛えるのか目的意識を持つことが何より大切だ」。五輪出場選手のトレーナーを
務めるR―body project(東京・渋谷)の鈴木岳代表はこう説明する。
■柔軟に動く関節に
同じスポーツ選手でも種目が違えば動き方が違うので、同じ筋肉でも鍛える目的が異なり
トレーニングの仕方も変わる。その前提になるのは肩や股関節のように動くべき関節が
広く柔軟に動き、腰椎など固定すべき骨をきちんと固定するように周辺の筋肉を鍛えることだ。
やみくもに筋肉を鍛えても動くべき関節が動きにくくなるなど、かえって運動能力は低下する
ことになりかねない。これは一般人でも同じことだ。
そこで大切になるのが、自分のからだのどこがおかしいかのチェックだ。
スポーツ選手では専門のトレーナーに点検してもらうが、一般の人が自分の立ち姿を鏡で
確認するだけでも、課題がいろいろ見えてくる。
例えば正しい姿勢で立ったつもりでも、腕がからだの真横にならず手の甲が正面から見える
ようだと、肩甲骨周りの筋肉が弱かったり背中の筋肉が硬かったりする。肩甲骨の周りの
筋肉が弱いと猫背になったり肩がこったりしやすい。そこで肩こりの解消や予防のために、
うつぶせの姿勢から肩甲骨を寄せて胸を開く運動をして肩甲骨を鍛えるわけだ。
何の目的のためにどのような理由でトレーニングするのかがわかれば、効果も感じやすい。
ファンクショナルトレーニングで従来にない器具を使ったり新しいトレーニング法を使ったり
することはほとんどない。ただトレーニングの目的と理由を明確にすることが重要で、同じ筋肉を
鍛える場合でも目的が異なればトレーニング法などが違ってくる。
従来の上半身を持ち上げる腹筋運動はボディービルなどには適しているが、運動を重視すると
腹筋だけでなく股関節周りの筋肉まで合わせて鍛える別のトレーニングがより適している。
一般の人の場合は日常生活に必要なからだの機能を高めることが大切なので、ものを持ち上げる
など日常に多い動作を取り入れたトレーニングも役に立つ。
■病気や障害を防止
ファンクショナルトレーニングの考え方を健康管理に取り入れたのが聖路加国際病院だ。
人間ドックなど予防医療の拠点として開設した付属クリニックの聖路加メディローカスに、R―bodyと
提携して同トレーニングを導入した。同病院の福井次矢院長は「健診での身体的な機能の確認と
目的に合ったトレーニングのプログラムを組み合わせることで、からだの機能を高め病気の予防にも
なる」と説明する。
これまでの人間ドックでは検査数値に基づいて運動の必要があると指導しても、具体的にどのような
理由でどんなトレーニングをしたらよいかまで踏み込んだ提案はなかった。そこにファンクショナル
トレーニングのチェックを加え、内科的な健康状態だけでなくからだの状態や機能に合わせた運動を
提案できる。福井院長は自身も実際に同トレーニングを試してみて「長年悩んでいた肩のこりなどが
なくなった」と笑う。
ファンクショナルトレーニングは動きを鍛えることで機能を向上するだけでなく、障害が起こるのを
防ぐことも目的だ。高齢化が進むにつれて足腰の機能の衰えによる転倒などが起こりやすくなるが、
機能を考えたトレーニングをすることで転倒予防だけでなく、転んでもけがをしにくいなど障害を防ぐ
効果も出る。
いくらトレーニングを積んでも、単に「体を鍛える」だけでは効果は限られる。年齢や自分のからだの
くせに合わせたトレーニングを、理解して実施することが、長続きにもつながる。運動の目的や
理由を考えることで、自分の健康のために何が必要かを見直すきっかけにもなりそうだ。
本日の担当:御殿場店 池谷 (日本経済新聞より)
一般向けのからだづくりに役立てようという動きが広がっている。
フィットネスクラブで取り入れる例が増えているだけでなく、医療機関も注目し始めた。
同トレーニングは「動きの質をあげる」とよくいわれるが、どんな特徴があり、どういった点に
気をつければよいのだろうか。
ファンクショナルトレーニングは直訳すると機能的なトレーニングだが、関節や筋肉を
効果的に使って目的に合わせた動きができるからだづくりをめざす。
筋トレとは違い「人間が生きる上で必要な、動きのトレーニングだ。正しい身体の知識を理解し、
何のために鍛えるのか目的意識を持つことが何より大切だ」。五輪出場選手のトレーナーを
務めるR―body project(東京・渋谷)の鈴木岳代表はこう説明する。
■柔軟に動く関節に
同じスポーツ選手でも種目が違えば動き方が違うので、同じ筋肉でも鍛える目的が異なり
トレーニングの仕方も変わる。その前提になるのは肩や股関節のように動くべき関節が
広く柔軟に動き、腰椎など固定すべき骨をきちんと固定するように周辺の筋肉を鍛えることだ。
やみくもに筋肉を鍛えても動くべき関節が動きにくくなるなど、かえって運動能力は低下する
ことになりかねない。これは一般人でも同じことだ。
そこで大切になるのが、自分のからだのどこがおかしいかのチェックだ。
スポーツ選手では専門のトレーナーに点検してもらうが、一般の人が自分の立ち姿を鏡で
確認するだけでも、課題がいろいろ見えてくる。
例えば正しい姿勢で立ったつもりでも、腕がからだの真横にならず手の甲が正面から見える
ようだと、肩甲骨周りの筋肉が弱かったり背中の筋肉が硬かったりする。肩甲骨の周りの
筋肉が弱いと猫背になったり肩がこったりしやすい。そこで肩こりの解消や予防のために、
うつぶせの姿勢から肩甲骨を寄せて胸を開く運動をして肩甲骨を鍛えるわけだ。
何の目的のためにどのような理由でトレーニングするのかがわかれば、効果も感じやすい。
ファンクショナルトレーニングで従来にない器具を使ったり新しいトレーニング法を使ったり
することはほとんどない。ただトレーニングの目的と理由を明確にすることが重要で、同じ筋肉を
鍛える場合でも目的が異なればトレーニング法などが違ってくる。
従来の上半身を持ち上げる腹筋運動はボディービルなどには適しているが、運動を重視すると
腹筋だけでなく股関節周りの筋肉まで合わせて鍛える別のトレーニングがより適している。
一般の人の場合は日常生活に必要なからだの機能を高めることが大切なので、ものを持ち上げる
など日常に多い動作を取り入れたトレーニングも役に立つ。
■病気や障害を防止
ファンクショナルトレーニングの考え方を健康管理に取り入れたのが聖路加国際病院だ。
人間ドックなど予防医療の拠点として開設した付属クリニックの聖路加メディローカスに、R―bodyと
提携して同トレーニングを導入した。同病院の福井次矢院長は「健診での身体的な機能の確認と
目的に合ったトレーニングのプログラムを組み合わせることで、からだの機能を高め病気の予防にも
なる」と説明する。
これまでの人間ドックでは検査数値に基づいて運動の必要があると指導しても、具体的にどのような
理由でどんなトレーニングをしたらよいかまで踏み込んだ提案はなかった。そこにファンクショナル
トレーニングのチェックを加え、内科的な健康状態だけでなくからだの状態や機能に合わせた運動を
提案できる。福井院長は自身も実際に同トレーニングを試してみて「長年悩んでいた肩のこりなどが
なくなった」と笑う。
ファンクショナルトレーニングは動きを鍛えることで機能を向上するだけでなく、障害が起こるのを
防ぐことも目的だ。高齢化が進むにつれて足腰の機能の衰えによる転倒などが起こりやすくなるが、
機能を考えたトレーニングをすることで転倒予防だけでなく、転んでもけがをしにくいなど障害を防ぐ
効果も出る。
いくらトレーニングを積んでも、単に「体を鍛える」だけでは効果は限られる。年齢や自分のからだの
くせに合わせたトレーニングを、理解して実施することが、長続きにもつながる。運動の目的や
理由を考えることで、自分の健康のために何が必要かを見直すきっかけにもなりそうだ。
本日の担当:御殿場店 池谷 (日本経済新聞より)
Posted by 保険カンパニー at
09:37
│Comments(0)
2014年08月26日
おもちゃで認知症予防
お年寄りの認知症予防に役立ててもらおうと20日、生駒市東松ヶ丘の集会場で記憶や
頭の柔軟性を試す創作おもちゃの展示体験会があり、約20人が実際に遊んで楽しんだ。
地域の健康づくりを目指すボランティアの吉村邦彦さん(71)らがペットボトルや空き箱、
空き缶などで作った37種類。参加者は工作用紙で作ったコマを回し、倒れたところに
書かれている設問に答えたり、ザルの中に五つのサイコロを振り、出た目の足し算が何秒で
できるか挑戦したりしたあと、自分がどのくらいできたかチェック表に書き込んだ。
市内の主婦石躍いさ子さん(70)は「簡単そうで、できないものもあって飽きませんね。
自分でも作ってみたい」と話していた。
おもちゃは来月24~30日、生駒駅前図書室内ギャラリーで展示する。
本日の担当:学園通り店 野口 (読売新聞より)
頭の柔軟性を試す創作おもちゃの展示体験会があり、約20人が実際に遊んで楽しんだ。
地域の健康づくりを目指すボランティアの吉村邦彦さん(71)らがペットボトルや空き箱、
空き缶などで作った37種類。参加者は工作用紙で作ったコマを回し、倒れたところに
書かれている設問に答えたり、ザルの中に五つのサイコロを振り、出た目の足し算が何秒で
できるか挑戦したりしたあと、自分がどのくらいできたかチェック表に書き込んだ。
市内の主婦石躍いさ子さん(70)は「簡単そうで、できないものもあって飽きませんね。
自分でも作ってみたい」と話していた。
おもちゃは来月24~30日、生駒駅前図書室内ギャラリーで展示する。
本日の担当:学園通り店 野口 (読売新聞より)
Posted by 保険カンパニー at
09:15
│Comments(0)
2014年08月25日
広島土砂災害 「警戒区域」指定に全国“格差”
土砂災害の恐れがある「土砂災害危険箇所」を、住民の避難態勢を整備する「土砂災害
警戒区域」などに切り替える取り組みが全国で進められているが、その進捗(しんちょく)を示す
「指定率」は都道府県によって大きく差が出ている。
指定が完了した県がある一方、10%台にとどまっているところもあるためだ。
■きっかけは平成11年の広島の土砂崩れ
警戒区域の指定には、地質調査や、防災情報をまとめたハザードマップ(災害予測地図)の
作製による住民への危険周知といった条件があり、指定を通じて防災意識の向上が期待されている。
だが、行政の人手不足や予算面などを理由に、切り替えが遅れているところも少なくない。
警戒区域は、より危険性が高い区域は特別警戒区域として指定。特別警戒区域の場合、建物の
移転勧告をすることもある。
この制度を創設するきっかけになったのは、平成11年6月に広島市と広島県呉市で起きた
土砂崩れなどで31人が死亡した災害だ。これを機に制定された土砂災害防止法に基づく制度で、
15年には広島県内13カ所で初の警戒区域の指定が行われた。
国土交通省によると、全国の土砂災害の危険箇所約52万カ所のうち、警戒区域に指定されて
いるのは約7割の約35万カ所。
広島県内の危険箇所は全国最多の約3万2千カ所を抱えるが、指定率は約37%にとどまっている。
県砂防課によると、住民説明などに手間がかかり、指定には2年以上かかることも。県の現状の
態勢では、指定完了には20年近くかかる見通しだ。今回の土砂災害で被害のあった区域のうち
指定されていたのは1区域のみ。残りの区域は「順番待ち」だった。
担当者によると、指定は公共施設がある地域や、過去に災害が起きた地域を優先。なかには
「地価の下落につながる恐れがある」と住民が指定を拒み、調査に入れないケースもある。
■福岡などは100%
一方、すでに指定が完了しているのは、青森、山梨、福岡の3県。福岡県では専門職員5人を
配置した上で、予算も数倍に増やした。
福岡県砂防課によると、21年7月の「中国・九州北部豪雨」による同県篠栗町での土砂災害で
2人が死亡したことが指定に本腰を入れる契機になった。避難の重要性を実感してもらう
ビデオも自作し、住民理解を得るのに苦心したという。
片田敏孝群馬大教授(災害社会工学)は、「警戒区域を指定することで危険な場所に住んで
いることの自覚が促され、住民は主体的に早めの行動を取るようになる。指定はかなり踏み込んだ
防災政策といえる。なかには、地価下落などを嫌がる住民の合意がとれずに指定が進まない例も
あるが、物理的な危険は同じで、本末転倒だ」と話している。
本日の担当:学園通り店 杉山 (産経新聞より)
警戒区域」などに切り替える取り組みが全国で進められているが、その進捗(しんちょく)を示す
「指定率」は都道府県によって大きく差が出ている。
指定が完了した県がある一方、10%台にとどまっているところもあるためだ。
■きっかけは平成11年の広島の土砂崩れ
警戒区域の指定には、地質調査や、防災情報をまとめたハザードマップ(災害予測地図)の
作製による住民への危険周知といった条件があり、指定を通じて防災意識の向上が期待されている。
だが、行政の人手不足や予算面などを理由に、切り替えが遅れているところも少なくない。
警戒区域は、より危険性が高い区域は特別警戒区域として指定。特別警戒区域の場合、建物の
移転勧告をすることもある。
この制度を創設するきっかけになったのは、平成11年6月に広島市と広島県呉市で起きた
土砂崩れなどで31人が死亡した災害だ。これを機に制定された土砂災害防止法に基づく制度で、
15年には広島県内13カ所で初の警戒区域の指定が行われた。
国土交通省によると、全国の土砂災害の危険箇所約52万カ所のうち、警戒区域に指定されて
いるのは約7割の約35万カ所。
広島県内の危険箇所は全国最多の約3万2千カ所を抱えるが、指定率は約37%にとどまっている。
県砂防課によると、住民説明などに手間がかかり、指定には2年以上かかることも。県の現状の
態勢では、指定完了には20年近くかかる見通しだ。今回の土砂災害で被害のあった区域のうち
指定されていたのは1区域のみ。残りの区域は「順番待ち」だった。
担当者によると、指定は公共施設がある地域や、過去に災害が起きた地域を優先。なかには
「地価の下落につながる恐れがある」と住民が指定を拒み、調査に入れないケースもある。
■福岡などは100%
一方、すでに指定が完了しているのは、青森、山梨、福岡の3県。福岡県では専門職員5人を
配置した上で、予算も数倍に増やした。
福岡県砂防課によると、21年7月の「中国・九州北部豪雨」による同県篠栗町での土砂災害で
2人が死亡したことが指定に本腰を入れる契機になった。避難の重要性を実感してもらう
ビデオも自作し、住民理解を得るのに苦心したという。
片田敏孝群馬大教授(災害社会工学)は、「警戒区域を指定することで危険な場所に住んで
いることの自覚が促され、住民は主体的に早めの行動を取るようになる。指定はかなり踏み込んだ
防災政策といえる。なかには、地価下落などを嫌がる住民の合意がとれずに指定が進まない例も
あるが、物理的な危険は同じで、本末転倒だ」と話している。
本日の担当:学園通り店 杉山 (産経新聞より)
Posted by 保険カンパニー at
09:27
│Comments(0)
2014年08月22日
MRSA:青い光で退治 患部に照射 マウス実験で成功
大阪市立大医学部の鶴田大輔教授らの研究グループは、抗生物質が効きにくい多剤耐性菌の
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染の新たな治療法として、抗生物質を使わず
患部に青い光を当てて菌を殺すことに、マウスの実験で成功したと発表した。感染症治療には
抗生物質が有効だが、多用すると新たな耐性菌を生む恐れがあり、新治療法の実用化が期待される。
21日、米オンライン科学誌プロス・ワンに掲載される。
鶴田教授によると、皮膚の傷にMRSAなど多剤耐性菌が感染すると治癒が遅れ、全身やけどでは
死亡するケースもあるという。
実験は、光の照射前にアミノ酸の一種の5−アミノレブリン酸(5−ALA)を注射する方法を使った。
増殖している菌は5−ALAを取り込み、5−ALAは菌の内部で、青い光を受けると活性酸素を
生じる物質に変化する。活性酸素は細胞膜を破壊し、菌を死滅させる。
免疫力を低下させたマウスの背中に直径6ミリの傷を作り、傷口にMRSAを感染させて治療法の
有効性を調べた。5−ALAを注射し、青色発光ダイオードで光を約1分間当てる治療を毎日続けると、
13日目で傷口が塞がり、菌の量は100分の1程度に減った。治療しないと傷口は2割程度しか
回復しなかったという。
MRSA以外での実験も、今後予定している。
鶴田教授は「数年内に感染症治療にも使えるようにしたい」と話している。
本日の担当:沼津店 山崎 (毎日新聞より)
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染の新たな治療法として、抗生物質を使わず
患部に青い光を当てて菌を殺すことに、マウスの実験で成功したと発表した。感染症治療には
抗生物質が有効だが、多用すると新たな耐性菌を生む恐れがあり、新治療法の実用化が期待される。
21日、米オンライン科学誌プロス・ワンに掲載される。
鶴田教授によると、皮膚の傷にMRSAなど多剤耐性菌が感染すると治癒が遅れ、全身やけどでは
死亡するケースもあるという。
実験は、光の照射前にアミノ酸の一種の5−アミノレブリン酸(5−ALA)を注射する方法を使った。
増殖している菌は5−ALAを取り込み、5−ALAは菌の内部で、青い光を受けると活性酸素を
生じる物質に変化する。活性酸素は細胞膜を破壊し、菌を死滅させる。
免疫力を低下させたマウスの背中に直径6ミリの傷を作り、傷口にMRSAを感染させて治療法の
有効性を調べた。5−ALAを注射し、青色発光ダイオードで光を約1分間当てる治療を毎日続けると、
13日目で傷口が塞がり、菌の量は100分の1程度に減った。治療しないと傷口は2割程度しか
回復しなかったという。
MRSA以外での実験も、今後予定している。
鶴田教授は「数年内に感染症治療にも使えるようにしたい」と話している。
本日の担当:沼津店 山崎 (毎日新聞より)
Posted by 保険カンパニー at
08:13
│Comments(0)
2014年08月21日
損保大手、11月にも再生医療保険を投入 日本の臨床研究、後押し
三井住友海上火災保険など損害保険大手が、iPS細胞(人工多能性幹細胞)などを使う
再生医療の臨床研究向け保険を11月にも投入することが17日までに、分かった。
治療で健康被害が生じた場合などに医療研究機関が患者へ支払う補償金を保険でカバーする。
患者だけでなく医師らも医療リスクに備えることができるようになり、日本が先行する
再生医療研究を後押しすると期待される。
前例のない臨床研究が多い再生医療分野は、治療のリスク評価が難しく、これまでは
損害保険の商品設計ができなかった。
しかし、再生医療を提供する病院がとるべき手続きなどを定めた「再生医療安全性確保法」が
昨年成立。11月に同法が施行されることに対応し、日本再生医療学会がこのほど被害補償の
指針をまとめ、これに沿って同学会と損保業界が保険制度の整備に乗り出した。
制度は、研究機関に明白な過失がない場合も被害補償し、補償に不服があった場合は、
同学会に設置する第三者機関に判断が委ねられる仕組み。現在詳細を詰めており、
補償対象には医療費や治療のための交通費負担などのほか、患者が死亡したり、障害が
生じた場合の逸失利益も含まれる見込み。
保険料は、病院などの研究機関が個別の研究ごとに支払い、研究の難易度で金額は変わる。
同学会によると、最大で年間20~30件の研究が保険対象となる可能性があるという。
政府は、新たな成長戦略で再生医療分野に期待を寄せており、研究の進展や関連産業の
拡大を促す制度整備に力を入れている。経済産業省によると、再生医療をめぐる国内の
市場規模は2030年に1.6兆円と、12年比で約60倍に拡大する見通しだ。
損保各社は、自動車保険などの既存商品の販売が国内で頭打ちになる中、成長が見込まれる
医療・健康分野の商品を収益源に育てたい考え。また、再生医療をめぐる法整備や学会による
補償指針の策定は日本が先行しており、関連の保険ノウハウを海外展開することも視野に
あるとみられる。
【用語解説】再生医療
病気や事故で失われた体の組織を再生させたり、機能を回復させたりするための医療。
ノーベル賞を受賞した山中伸弥・京都大教授が開発したiPS細胞(人工多能性幹細胞)は、
さまざまな臓器や組織の細胞になる能力を持ち、再生医療の飛躍的な発展が期待されている。
本日の担当:沼津店 坂倉 (産経新聞より)
再生医療の臨床研究向け保険を11月にも投入することが17日までに、分かった。
治療で健康被害が生じた場合などに医療研究機関が患者へ支払う補償金を保険でカバーする。
患者だけでなく医師らも医療リスクに備えることができるようになり、日本が先行する
再生医療研究を後押しすると期待される。
前例のない臨床研究が多い再生医療分野は、治療のリスク評価が難しく、これまでは
損害保険の商品設計ができなかった。
しかし、再生医療を提供する病院がとるべき手続きなどを定めた「再生医療安全性確保法」が
昨年成立。11月に同法が施行されることに対応し、日本再生医療学会がこのほど被害補償の
指針をまとめ、これに沿って同学会と損保業界が保険制度の整備に乗り出した。
制度は、研究機関に明白な過失がない場合も被害補償し、補償に不服があった場合は、
同学会に設置する第三者機関に判断が委ねられる仕組み。現在詳細を詰めており、
補償対象には医療費や治療のための交通費負担などのほか、患者が死亡したり、障害が
生じた場合の逸失利益も含まれる見込み。
保険料は、病院などの研究機関が個別の研究ごとに支払い、研究の難易度で金額は変わる。
同学会によると、最大で年間20~30件の研究が保険対象となる可能性があるという。
政府は、新たな成長戦略で再生医療分野に期待を寄せており、研究の進展や関連産業の
拡大を促す制度整備に力を入れている。経済産業省によると、再生医療をめぐる国内の
市場規模は2030年に1.6兆円と、12年比で約60倍に拡大する見通しだ。
損保各社は、自動車保険などの既存商品の販売が国内で頭打ちになる中、成長が見込まれる
医療・健康分野の商品を収益源に育てたい考え。また、再生医療をめぐる法整備や学会による
補償指針の策定は日本が先行しており、関連の保険ノウハウを海外展開することも視野に
あるとみられる。
【用語解説】再生医療
病気や事故で失われた体の組織を再生させたり、機能を回復させたりするための医療。
ノーベル賞を受賞した山中伸弥・京都大教授が開発したiPS細胞(人工多能性幹細胞)は、
さまざまな臓器や組織の細胞になる能力を持ち、再生医療の飛躍的な発展が期待されている。
本日の担当:沼津店 坂倉 (産経新聞より)
Posted by 保険カンパニー at
10:02
│Comments(0)