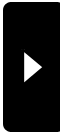2014年07月11日
ヤフー地図に熱中症危険度
ヤフーは7日から、インターネットの無料地図サービス「Yahoo!地図」で、
熱中症になる危険度を地図上に示すサービスを始めた。9月30日まで。
日本気象協会が観測した国内142か所について、「危険」「厳重警戒」「警戒」
「注意」「ほぼ安全」の5段階で危険度を表示する。気温や湿度を基に判断し、
情報は朝、昼、夕方の1日3回、更新する。
2日後までの予測も示す。スマートフォンやタブレット型端末で「Yahoo!地図」の
アプリをダウンロードして特定の地域を設定すると、「危険」「厳重警戒」になった場合に
通知される機能も設けた。アドレスは、http://map.yahoo.co.jp/。
本日の担当:沼津店 坂倉 (読売新聞より)
熱中症になる危険度を地図上に示すサービスを始めた。9月30日まで。
日本気象協会が観測した国内142か所について、「危険」「厳重警戒」「警戒」
「注意」「ほぼ安全」の5段階で危険度を表示する。気温や湿度を基に判断し、
情報は朝、昼、夕方の1日3回、更新する。
2日後までの予測も示す。スマートフォンやタブレット型端末で「Yahoo!地図」の
アプリをダウンロードして特定の地域を設定すると、「危険」「厳重警戒」になった場合に
通知される機能も設けた。アドレスは、http://map.yahoo.co.jp/。
本日の担当:沼津店 坂倉 (読売新聞より)
Posted by 保険カンパニー at
09:17
│Comments(0)
2014年07月10日
厚労白書、健康寿命をより長く
厚生労働省がまとめた2014年版の厚生労働白書の概要が8日、分かった。
健康に日常生活を送れる「健康寿命」は平均寿命に比べ、男性は約9年、
女性は約13年短く、健康寿命を延ばす重要性を訴えた。
二つの寿命の差が開くと、医療や介護の費用が重くなるためだ。
白書によると、男性は平均寿命79・55歳に対し、健康寿命は70・42歳で9・13年短い。
女性の平均寿命は86・30歳で、健康寿命は73・62歳。2種類の寿命がいずれも
男性より長かったが、その差はより開き、健康寿命が12・68年短かった。
本日の担当:御殿場店 池谷 (新潟日報より)
健康に日常生活を送れる「健康寿命」は平均寿命に比べ、男性は約9年、
女性は約13年短く、健康寿命を延ばす重要性を訴えた。
二つの寿命の差が開くと、医療や介護の費用が重くなるためだ。
白書によると、男性は平均寿命79・55歳に対し、健康寿命は70・42歳で9・13年短い。
女性の平均寿命は86・30歳で、健康寿命は73・62歳。2種類の寿命がいずれも
男性より長かったが、その差はより開き、健康寿命が12・68年短かった。
本日の担当:御殿場店 池谷 (新潟日報より)
Posted by 保険カンパニー at
09:31
│Comments(0)
2014年07月09日
気になる台風情報 - 台風8号接近に伴い発表された特別警報の判断基準とは
台風8号の接近に伴い、気象庁は7月8日午前中までに沖縄本島などへの特別警報を
発表し、宜野湾市などには避難勧告も出された。
7月に日本列島に影響を与える台風としては「過去最強クラス」の台風ということで
出された「特別警報」。その判断基準はどのようになっているのかをまとめた。
気象庁が従来の「警報」に加え、「警報の発表基準をはるかに超える豪雨や大津波」などが
予想される際に発表する「特別警報」の運用を開始したのは、2013年8月30日。
気象庁によると、特別警報の対象となる現象は「東日本大震災」や国内観測史上最高の
潮位を記録した「伊勢湾台風」などで、いずれも甚大な被害が出た災害ばかりとなっている。
特別警報が発表される詳細な基準は下記の通り。
◆大雨
「台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨」もしくは「数十年に一度の
強度の台風や同程度の温帯低気圧による大雨」が予想される場合に発表。
◆暴風・高潮・高波
「数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧」によって暴風、高潮、
高波が予想される場合に発表。
この他にも大雪や津波、火山噴火などの基準も気象庁で公開されている。
特別警報が発表されたら、同庁は「ただちに命を守る行動」を取るよう、注意および最大級の
警戒を呼びかけている。具体的には「避難所へ避難する」「外出することが危険な場合は
家の中で安全な場所にとどまる」ことなどを挙げている。
8日10時54分の時点で、沖縄本島では南風原町を除くほぼすべての全域において暴風、
波浪、高波の特別警報が発令中となっているほか、鹿児島県も一部地域で波浪警報が出されている。
なお、最新の気象情報は気象庁で確認できる。
本日の担当:御殿場店 田邉 (マイナビニュースより)
発表し、宜野湾市などには避難勧告も出された。
7月に日本列島に影響を与える台風としては「過去最強クラス」の台風ということで
出された「特別警報」。その判断基準はどのようになっているのかをまとめた。
気象庁が従来の「警報」に加え、「警報の発表基準をはるかに超える豪雨や大津波」などが
予想される際に発表する「特別警報」の運用を開始したのは、2013年8月30日。
気象庁によると、特別警報の対象となる現象は「東日本大震災」や国内観測史上最高の
潮位を記録した「伊勢湾台風」などで、いずれも甚大な被害が出た災害ばかりとなっている。
特別警報が発表される詳細な基準は下記の通り。
◆大雨
「台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨」もしくは「数十年に一度の
強度の台風や同程度の温帯低気圧による大雨」が予想される場合に発表。
◆暴風・高潮・高波
「数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧」によって暴風、高潮、
高波が予想される場合に発表。
この他にも大雪や津波、火山噴火などの基準も気象庁で公開されている。
特別警報が発表されたら、同庁は「ただちに命を守る行動」を取るよう、注意および最大級の
警戒を呼びかけている。具体的には「避難所へ避難する」「外出することが危険な場合は
家の中で安全な場所にとどまる」ことなどを挙げている。
8日10時54分の時点で、沖縄本島では南風原町を除くほぼすべての全域において暴風、
波浪、高波の特別警報が発令中となっているほか、鹿児島県も一部地域で波浪警報が出されている。
なお、最新の気象情報は気象庁で確認できる。
本日の担当:御殿場店 田邉 (マイナビニュースより)
Posted by 保険カンパニー at
10:03
│Comments(0)
2014年07月08日
コンビニ:「飽和」指摘も5万店 年間売上高10兆円目前
大手コンビニエンスストア10社の店舗数は5月末現在、5万480店。
前年同月に比べ5.3%増えた。年間売上高は約9兆4000億円に上り、百貨店を約3兆円
上回る。国内5万店は「飽和水準」ともいわれるが、セブン−イレブンやファミリーマートの
今年度の出店計画は、いずれも過去最高の1600店。高齢化に対応した宅配サービスなど
時代のニーズを取り込みながら、新たな出店余地を開拓し続けている。
米国生まれのコンビニだが、米国内では伝統的にガソリンスタンド内の小型店舗が強く、
日本型コンビニは少数派。市街地に複数店舗が密集するようなケースは海外ではほとんど
見られず、日本は世界に例のないコンビニ大国となった。
都道府県別でみると、店舗が最も多いのは東京都。
大手5社で6519店が出店。人口10万人あたりに49店がある計算で、コンビニの
密集度合いでも日本一だ。密集度の2番手は宮城県で、10万人あたりに45店。
次いで愛知県の44店と続く。逆に最も店舗が少ないのは高知県の172店。
10万人あたりに22店で、密集度は東京都の半分以下だ。
国内でコンビニの本格展開が始まったのは40年前。
大手スーパーのイトーヨーカ堂が米国のセブンの運営会社とライセンス契約を結び、
1974年5月、東京都江東区豊洲にセブン1号店を出店した。翌年にはダイエーがローソンを
設立し、81年には西友ストアー(現西友)のコンビニ事業を引き継いでファミマが発足。
大競争時代が始まった。
飛躍のきっかけになったのが、おにぎりの商品開発だ。
家で作るのが一般的だった時代、セブンは原材料やごはんの炊き方を研究。
パリッとしたのりの食感を楽しめる包装フィルムを開発し、78年に発売して大ヒット。
他社も追随し、コンビニの主力商品となった。
80年代以降、個々の商品がいつ、どの程度売れたのかを瞬時に把握するPOS
(販売時点情報管理)システムの導入が進んだ。売れ筋商品の仕入れを増やし、売れない
商品を売り場から外すなど、頻繁に商品を入れ替え、コンビニは収益力を高めていった。
◇宅配サービスや共同出店を加速
80年代後半になると、コンビニはさらなる進化をとげる。単身世帯や働く女性が増える中、
「24時間営業」の利点を生かし、電気、ガス料金の収納業務や、ATM(現金自動受払機)
設置、住民票の発行などのサービスを次々と導入。
単なる小売店ではなく、社会インフラとしての役割も増していった。2011年の東日本大震災では、
大手3社の東北地方の店の8割が約2週間で復旧。被災地への食品の供給を段階的に再開し、
ライフラインとしての役割も注目された。
積極出店を受け、都市部や地方の幹線道路沿いなど従来型の「一等地」は減っている。
各社ともJRや私鉄の駅構内のいわゆる「エキナカ」や病院内など、従来になかった場所への
出店を強化。カラオケ店や薬局などとの共同出店も目立つようになった。
高齢者の増加に対応し、宅配サービスも充実させている。電話やインターネットで注文をすると
弁当を届けたり、一部店舗では食品以外の商品も宅配したりするなど現代の「御用聞き」の
役割も担い、新たな顧客層を開拓している。
◇日本モデルでの海外展開困難も
海外展開も欠かせない戦略だ。セブンは現在、海外15カ国に3万6000超の店舗がある。
05年には本家、米国のセブン−イレブンを子会社化し、日本型の運営手法を注入。業績を向上させた。
他社もアジアを中心に日本モデルのコンビニ輸出を進めている。
ただ海外展開にはリスクもつきまとう。ファミマは今年5月、約8000店舗を展開していた
韓国市場から撤退。独立志向が強い合弁相手との戦略の違いが出たのが原因とみられる。
ミニストップもカザフスタンからの撤退を決めた。
国内外での拡大路線は、一筋縄ではいかない時代に入っている。
本日の担当:学園通り店 長山 (毎日新聞より)
前年同月に比べ5.3%増えた。年間売上高は約9兆4000億円に上り、百貨店を約3兆円
上回る。国内5万店は「飽和水準」ともいわれるが、セブン−イレブンやファミリーマートの
今年度の出店計画は、いずれも過去最高の1600店。高齢化に対応した宅配サービスなど
時代のニーズを取り込みながら、新たな出店余地を開拓し続けている。
米国生まれのコンビニだが、米国内では伝統的にガソリンスタンド内の小型店舗が強く、
日本型コンビニは少数派。市街地に複数店舗が密集するようなケースは海外ではほとんど
見られず、日本は世界に例のないコンビニ大国となった。
都道府県別でみると、店舗が最も多いのは東京都。
大手5社で6519店が出店。人口10万人あたりに49店がある計算で、コンビニの
密集度合いでも日本一だ。密集度の2番手は宮城県で、10万人あたりに45店。
次いで愛知県の44店と続く。逆に最も店舗が少ないのは高知県の172店。
10万人あたりに22店で、密集度は東京都の半分以下だ。
国内でコンビニの本格展開が始まったのは40年前。
大手スーパーのイトーヨーカ堂が米国のセブンの運営会社とライセンス契約を結び、
1974年5月、東京都江東区豊洲にセブン1号店を出店した。翌年にはダイエーがローソンを
設立し、81年には西友ストアー(現西友)のコンビニ事業を引き継いでファミマが発足。
大競争時代が始まった。
飛躍のきっかけになったのが、おにぎりの商品開発だ。
家で作るのが一般的だった時代、セブンは原材料やごはんの炊き方を研究。
パリッとしたのりの食感を楽しめる包装フィルムを開発し、78年に発売して大ヒット。
他社も追随し、コンビニの主力商品となった。
80年代以降、個々の商品がいつ、どの程度売れたのかを瞬時に把握するPOS
(販売時点情報管理)システムの導入が進んだ。売れ筋商品の仕入れを増やし、売れない
商品を売り場から外すなど、頻繁に商品を入れ替え、コンビニは収益力を高めていった。
◇宅配サービスや共同出店を加速
80年代後半になると、コンビニはさらなる進化をとげる。単身世帯や働く女性が増える中、
「24時間営業」の利点を生かし、電気、ガス料金の収納業務や、ATM(現金自動受払機)
設置、住民票の発行などのサービスを次々と導入。
単なる小売店ではなく、社会インフラとしての役割も増していった。2011年の東日本大震災では、
大手3社の東北地方の店の8割が約2週間で復旧。被災地への食品の供給を段階的に再開し、
ライフラインとしての役割も注目された。
積極出店を受け、都市部や地方の幹線道路沿いなど従来型の「一等地」は減っている。
各社ともJRや私鉄の駅構内のいわゆる「エキナカ」や病院内など、従来になかった場所への
出店を強化。カラオケ店や薬局などとの共同出店も目立つようになった。
高齢者の増加に対応し、宅配サービスも充実させている。電話やインターネットで注文をすると
弁当を届けたり、一部店舗では食品以外の商品も宅配したりするなど現代の「御用聞き」の
役割も担い、新たな顧客層を開拓している。
◇日本モデルでの海外展開困難も
海外展開も欠かせない戦略だ。セブンは現在、海外15カ国に3万6000超の店舗がある。
05年には本家、米国のセブン−イレブンを子会社化し、日本型の運営手法を注入。業績を向上させた。
他社もアジアを中心に日本モデルのコンビニ輸出を進めている。
ただ海外展開にはリスクもつきまとう。ファミマは今年5月、約8000店舗を展開していた
韓国市場から撤退。独立志向が強い合弁相手との戦略の違いが出たのが原因とみられる。
ミニストップもカザフスタンからの撤退を決めた。
国内外での拡大路線は、一筋縄ではいかない時代に入っている。
本日の担当:学園通り店 長山 (毎日新聞より)
Posted by 保険カンパニー at
09:17
│Comments(0)
2014年07月07日
介護保険の2割負担 個々の所得で判断、倍額とは限らず
「地域医療・介護総合確保推進法(医療と介護の確保に関する法律)」が成立し、介護保険でも
さまざまな変更が行われる。介護サービスの利用料は制度発足当初から1割負担だったが、
平成27年8月から一定以上の所得の人は2割負担になる。負担が1割か2割かは、サービスを
利用する個々の所得で決まる。2割負担になっても、費用は必ずしも倍額にはならない。
慌ててサービスを削ることのないようにしたい。
埼玉県川越市に住む川崎功さん(69)=仮名=は介護保険制度の改正が気がかりだった。
自己負担はこれまで誰でも1割だったが、今回の改正で、一定以上の所得の人は2割負担に
なることが昨年来、報道されていたからだ。
功さんの生活は、妻、恵子さん(65)=同=の介護が中心になっている。恵子さんは5年前に
脳出血で倒れ、要介護度は最重度の「5」。以前は座った姿勢が保てず、寝たきりだったが、
最近はリハビリの成果が出たのか、車椅子に座って過ごせるようになった。
目に入る風景が変わり、表情も明るくなったようだ。
恵子さんが使う介護保険のサービスは、週3日のデイケア、デイケア前の訪問介護、
週1回の訪問看護など。他に介護ベッドや車椅子も借りており、限度額はほぼいっぱい。
毎月、利用料として1割に当たる約3万5千円を払う。
功さんは「これ以外に訪問診療や薬代などの医療費もかかる。介護サービスが2割負担に
なって、3万5千円が7万円になったら、いったい何を減らせばいいのかと思っていた」と話す。
功さんが心配したのは、自身が元サラリーマンで、約380万円という比較的豊かな年金
収入があるからだ。だが、恵子さんの費用負担は1割で変わらない。1割か2割かは世帯の
所得ではなく、サービスを利用している個々の所得で決まる。
恵子さんには基礎年金の収入しかないからだ。
2割負担になる人の基準は「合計所得が160万円以上」。年金収入だけなら280万円以上に
当たり、介護保険の被保険者の所得上位20%を占める。来年8月以降、功さん自身が
介護サービスを使うことがあれば、功さんは2割負担だが、恵子さんは1割のままだ。
だが、個人単位で所得を見ることにした結果、2割負担の人の世帯が、夫婦とも1割負担の
世帯よりも世帯収入が少ない「逆転現象」も生じそうだ。
健康保険にも、高齢でも窓口負担が3割になる所得階層があるが、介護保険の方が対象範囲は
広い。功さんは「(基準となる)年収280万円は高収入とはいえないのでは…」と漏らす。
厚生労働省は「1割負担の人が2割になっても、利用料は2倍になるわけではない」と理解を
求める。介護保険には、自己負担が一定限度を超えたときに、負担額が頭打ちになる
「高額介護サービス費」があるためだ。頭打ちになる額は一般的な課税所得の人で3万7200円。
所得の高い人には4万4400円のカテゴリーが設けられる予定。
仮に要介護5で限度額いっぱいのサービスを使う人が2割負担になっても、自己負担は7万円では
なく、4万4400円か3万7200円になる見通し。詳細はケアマネジャーに相談したい。
功さんは「とりあえず、2割負担でないと分かってほっとした」と言う。胸をなでおろしつつ、
「負担が上がるのは仕方ない。保険料は上げてもいいが、利用料は上げてほしくない。
一番心配なのは費用のこと。状態が悪いときに支払う利用料が上がるのは不安が大きい」と
話している。
■配偶者課税なら施設利用料は増
恵子さんの負担割合が変わらないことに安堵(あんど)した功さんだが、気がかりはある。
仮に恵子さんが施設入所をした場合、費用は上がる見通しになったからだ。
今回の改正で、特別養護老人ホーム(特養)などに入所する低所得の人への費用補助
(補足給付)の仕組みも見直された。現在、グループ単位で生活する「ユニット型個室」の
特養に入所した場合、標準的な利用料は月額13万円以上。
食費、居住費、介護保険の1割負担などが含まれており、所得によって利用料が異なる。
現行制度では、恵子さんのように自身は課税されないが、夫には課税所得がある人が入所した
場合も負担は軽減される。世帯分離をすれば、恵子さん自身は「低所得者」と見なされるためだ。
恵子さんの場合、入所すると、月に13万円以上の入所費が5・2万円程度に下がり、差額は
介護保険から施設に補填(ほてん)される。
だが、制度改正で、配偶者が課税されている場合、負担軽減はされなくなる。
低所得の人への福祉的給付を、世帯の所得にかかわらず出すのは好ましくないとの考え方だ。
とはいえ、入所中で負担増になる人には打撃が大きい。施設によっては20万円近い利用料を
設定している所もあり、負担が一気に跳ね上がりかねない。何らかの激変緩和措置が要りそうだが、
厚生労働省は「経過措置を講じる予定は今のところない」としている。
このほか、預貯金などが一定額を超える人も費用補助の対象から外れる。
目安は単身で1千万円超、夫婦世帯で2千万円超で、不正受給者には加算金が課される。
当初は一定の評価額を超える不動産を所有している場合にも対象外とする方針だったが、
今回は見送られた。
本日の担当:学園通り店 野口 (産経新聞より)
さまざまな変更が行われる。介護サービスの利用料は制度発足当初から1割負担だったが、
平成27年8月から一定以上の所得の人は2割負担になる。負担が1割か2割かは、サービスを
利用する個々の所得で決まる。2割負担になっても、費用は必ずしも倍額にはならない。
慌ててサービスを削ることのないようにしたい。
埼玉県川越市に住む川崎功さん(69)=仮名=は介護保険制度の改正が気がかりだった。
自己負担はこれまで誰でも1割だったが、今回の改正で、一定以上の所得の人は2割負担に
なることが昨年来、報道されていたからだ。
功さんの生活は、妻、恵子さん(65)=同=の介護が中心になっている。恵子さんは5年前に
脳出血で倒れ、要介護度は最重度の「5」。以前は座った姿勢が保てず、寝たきりだったが、
最近はリハビリの成果が出たのか、車椅子に座って過ごせるようになった。
目に入る風景が変わり、表情も明るくなったようだ。
恵子さんが使う介護保険のサービスは、週3日のデイケア、デイケア前の訪問介護、
週1回の訪問看護など。他に介護ベッドや車椅子も借りており、限度額はほぼいっぱい。
毎月、利用料として1割に当たる約3万5千円を払う。
功さんは「これ以外に訪問診療や薬代などの医療費もかかる。介護サービスが2割負担に
なって、3万5千円が7万円になったら、いったい何を減らせばいいのかと思っていた」と話す。
功さんが心配したのは、自身が元サラリーマンで、約380万円という比較的豊かな年金
収入があるからだ。だが、恵子さんの費用負担は1割で変わらない。1割か2割かは世帯の
所得ではなく、サービスを利用している個々の所得で決まる。
恵子さんには基礎年金の収入しかないからだ。
2割負担になる人の基準は「合計所得が160万円以上」。年金収入だけなら280万円以上に
当たり、介護保険の被保険者の所得上位20%を占める。来年8月以降、功さん自身が
介護サービスを使うことがあれば、功さんは2割負担だが、恵子さんは1割のままだ。
だが、個人単位で所得を見ることにした結果、2割負担の人の世帯が、夫婦とも1割負担の
世帯よりも世帯収入が少ない「逆転現象」も生じそうだ。
健康保険にも、高齢でも窓口負担が3割になる所得階層があるが、介護保険の方が対象範囲は
広い。功さんは「(基準となる)年収280万円は高収入とはいえないのでは…」と漏らす。
厚生労働省は「1割負担の人が2割になっても、利用料は2倍になるわけではない」と理解を
求める。介護保険には、自己負担が一定限度を超えたときに、負担額が頭打ちになる
「高額介護サービス費」があるためだ。頭打ちになる額は一般的な課税所得の人で3万7200円。
所得の高い人には4万4400円のカテゴリーが設けられる予定。
仮に要介護5で限度額いっぱいのサービスを使う人が2割負担になっても、自己負担は7万円では
なく、4万4400円か3万7200円になる見通し。詳細はケアマネジャーに相談したい。
功さんは「とりあえず、2割負担でないと分かってほっとした」と言う。胸をなでおろしつつ、
「負担が上がるのは仕方ない。保険料は上げてもいいが、利用料は上げてほしくない。
一番心配なのは費用のこと。状態が悪いときに支払う利用料が上がるのは不安が大きい」と
話している。
■配偶者課税なら施設利用料は増
恵子さんの負担割合が変わらないことに安堵(あんど)した功さんだが、気がかりはある。
仮に恵子さんが施設入所をした場合、費用は上がる見通しになったからだ。
今回の改正で、特別養護老人ホーム(特養)などに入所する低所得の人への費用補助
(補足給付)の仕組みも見直された。現在、グループ単位で生活する「ユニット型個室」の
特養に入所した場合、標準的な利用料は月額13万円以上。
食費、居住費、介護保険の1割負担などが含まれており、所得によって利用料が異なる。
現行制度では、恵子さんのように自身は課税されないが、夫には課税所得がある人が入所した
場合も負担は軽減される。世帯分離をすれば、恵子さん自身は「低所得者」と見なされるためだ。
恵子さんの場合、入所すると、月に13万円以上の入所費が5・2万円程度に下がり、差額は
介護保険から施設に補填(ほてん)される。
だが、制度改正で、配偶者が課税されている場合、負担軽減はされなくなる。
低所得の人への福祉的給付を、世帯の所得にかかわらず出すのは好ましくないとの考え方だ。
とはいえ、入所中で負担増になる人には打撃が大きい。施設によっては20万円近い利用料を
設定している所もあり、負担が一気に跳ね上がりかねない。何らかの激変緩和措置が要りそうだが、
厚生労働省は「経過措置を講じる予定は今のところない」としている。
このほか、預貯金などが一定額を超える人も費用補助の対象から外れる。
目安は単身で1千万円超、夫婦世帯で2千万円超で、不正受給者には加算金が課される。
当初は一定の評価額を超える不動産を所有している場合にも対象外とする方針だったが、
今回は見送られた。
本日の担当:学園通り店 野口 (産経新聞より)
Posted by 保険カンパニー at
09:23
│Comments(0)